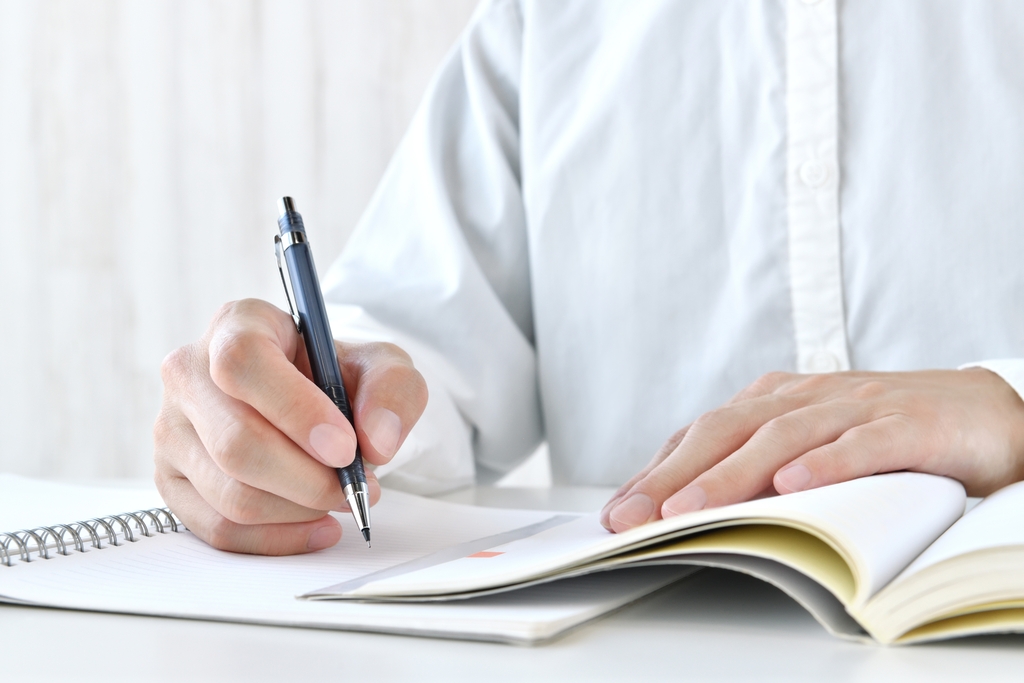SPIの非言語分野
SPIは、リクルート社が提供する適性検査の一種で、多くの企業が新卒採用時に活用しています。大きく「能力検査」と「性格検査」に分かれ、さらに能力検査は「言語」「非言語」の2分野のほか、企業や業界によっては「英語(SPI英語)」が課される場合もあります。
言語分野は主に語彙や読解力を問う問題ですが、今回フォーカスするのは「非言語分野」。こちらは数学的な思考力や論理力、情報処理の速さなどが求められ、就活生の中には苦手意識を持つ人も多い分野です。しかし、問題のパターンを知り、慣れておくことで得点アップが狙えるため、対策次第で大きく差がつく分野でもあります。
関連リンク:https://br-campus.jp/articles/report/2110
SPI非言語の知っておきたい基本事項
SPIの非言語分野は、「数的推理」や「資料の読み取り」など、数字や論理に基づく出題が中心です。数学が苦手な人ほど構えてしまいがちですが、出題には一定の傾向があるため、コツを掴めば効率よく対策できます。まずは基本の特徴から確認しておきましょう。
出題問題は中学~高校レベル
SPIの非言語分野では、「割合」「損益」「速さ」「表の読み取り」など、主に中学〜高校初級レベルの数学知識が問われます。いわゆる入試問題のような複雑さはなく、基本的な計算力と論理的な考え方があれば十分対応可能です。むしろ、苦手意識で手を止めてしまうことの方がもったいない分野。出題パターンに慣れ、解き方のコツを押さえておけば、着実に点数を積み上げることができるのです。
まずは基礎から丁寧に復習することが、高得点への近道でしょう。
出題問題数が多い
SPI非言語の試験は、1問1問のレベルは決して高くないものの、出題数が多く、時間との勝負になるのが特徴です。受検形式によって異なりますが、たとえばテストセンター方式の場合、非言語分野で30問近く出題されることがあり、制限時間は40分程度。単純計算でも、1問あたりにかけられる時間は1分強しかありません。中には図や表を使ってじっくり考える問題も含まれているため、すべてを丁寧に解こうとすると時間が足りなくなるケースも。あらかじめ頻出パターンに慣れておき、解ける問題から確実にこなす“割り切り”も重要です。
高得点を求められる
SPIの合格ラインは企業によって異なりますが、一般的には全体の6〜7割正答が目安と言われています。特に人気の高い大手企業や難関業界では、応募者のレベルも高いため、7〜8割以上の得点が求められるケースも珍しくありません。
SPIは足切りに使われることが多く、筆記での脱落を避けるには確実な得点力が必要です。「とりあえず受けてみる」では通過できない可能性があるため、事前の対策と繰り返しの演習が合否を分けるポイントになります。
SPI非言語は企業によって重要度が異なる
SPIを重視するかどうかは企業によってさまざまです。重視しない企業もある一方で、「基礎的な能力」を客観的に評価したい企業では、SPIのスコアが選考の重要な判断材料になります。特に人物像よりも能力評価に比重を置く傾向のある大手や専門職系の企業では、非言語分野の得点もシビアに見られる可能性があるため、油断せず準備しておくのが得策です。
SPI非言語のやっておくべき対策
SPIの非言語分野は、問題を読む・理解する・計算するという一連の作業に時間がかかるため、言語分野よりも対策に手間がかかるのが特徴です。苦手意識がある人ほど、早めの準備がカギになります。
①公式や数式などのパターンを暗記する
SPIの非言語分野では、出題される“問題そのもの”よりも、「この場面ではこの公式を使う」「あのパターンならこう解く」という型を覚えておくことが非常に重要です。
例えば「速さ=距離÷時間」「割合=比較する量÷元の量」「集合の公式=|A∪B|=|A|+|B|−|A∩B|」といった基本公式を、頭のなかで瞬時に引き出せるようにしておくと、解答スピードが格段に上がります。
対策方法としておすすめなのは、まず「頻出公式・数式」を一覧にして暗記し、それを用いた「典型問題」をひたすら解くことです。単に丸暗記するのではなく、「どの公式が、どんな問題文・どんな条件で使われるか」を意識しながら学習することで、応用問題にも対応できるようになります。
本番では時間との勝負です。公式を思い出す時間が少しでも短ければ、その分解答に回せる時間が増えます。公式・数式・解法パターンを“身体で覚える”レベルまで反復しておきましょう。
②苦手な問題は解説を確認する
SPIの非言語対策では、つまずいた問題を放置せず「解説を確認して理解する」ことが非常に重要です。特に、どの公式を使えば良いのか迷ったり、時間がかかってしまったりする問題は、あなたの“苦手分野”のサイン。演習のあとには必ず解けなかった問題を見直し、解説で「なぜこの公式を使ったのか」「どこで読み間違えたか」を丁寧にチェックしましょう。繰り返し確認することで、次に同じような問題に出会ったとき、迷わず解答に進めるようになるでしょう。
苦手な問題は、あなたの得点差となりうる部分です。解説を武器に、確実に潰していきましょう。
③模擬試験を活用する
模擬試験は、「実戦慣れ」をつけるための重要なステップです。理論的な公式を覚え、苦手分野を潰したら、次は本番に近い形式・制限時間で問題を解いてみましょう。
例えば、非言語分野では制限時間が厳しく、1問あたりの解答時間が短いため、ペース配分や解き慣れが得点差を生みます。模擬試験を使って「時間内にどれだけ正確に解けるか」を把握し、解けなかった問題の傾向を分析することで、効率的な演習が可能になります。
また、模擬試験用に用意された環境(WEBテスト形式/テストセンター形式)で練習しておくと、緊張感や操作感にも備えられ、本番で落ち着いて臨めるようになります。
練習量を確保し、自信を持って本番に向かいましょう。
SPI非言語の例題と解き方のコツ
SPI非言語では、割合・速さ・集合・表の読み取りなど、数字や論理を扱う典型問題が出題されます。よく出る問題の例題を取り上げながら、時間内に正答を導くためのコツや考え方についてみていきましょう。
【例題】推論
【問題】
Aさん、Bさん、Cさんの3人が話しています。
A:「私は嘘をつきません。」
B:「Cは嘘をついています。」
C:「Aは本当のことを言っています。」
ただし、3人のうち正直者は1人だけで、あとの2人は常に嘘をつきます。
このとき、正直者は誰か?
【選択肢】
A:Aさん B:Bさん C:Cさん
【正解】
B(Bさん)
【解説】
前提:「正直者は1人だけ」「嘘つきは常に嘘」
・Aが正直者だと仮定
A:「私は嘘をつきません」…真。
C:「Aは本当のことを言っています」…真になってしまう→正直者が2人で矛盾。
→A正直者は不成立。
・Bが正直者だと仮定
B:「Cは嘘をついています」…真→Cは嘘つき。
Cは「Aは本当のことを言っています」と発言→嘘なのでAは嘘つき。
Aの「私は嘘をつきません」は嘘→整合。
→正直者はBだけで条件クリア。
・Cが正直者だと仮定
C:「Aは本当のことを言っています」…真→Aも正直者に。
→正直者が2人で矛盾。
→C正直者は不成立。
解き方のコツ
まず、問題文を「丁寧に読み込む」ことが極めて重要です。条件や発言、前提が複数ある場合、読み飛ばしや誤読で誤答を招くケースが多いため、焦らず一文ずつ理解しましょう。
次に、「情報を図・表・式などで整理」すると効果的です。頭の中だけで考えるより、紙に書き出すことで関係性が可視化され、正しい結論を導きやすくなります。
そして、「パターンを押さえて慣れておく」こと。SPIの推論問題は出題形式がある程度固定されており、典型的なパターンを繰り返し練習することで、解答時間も短縮できます。
この3ステップを習慣化することで、推論問題に対して焦らず対応できる力が養われます。
【例題】集合
【問題】
あるクラスの生徒40人のうち、「英語が得意」と答えたのは25人、「数学が得意」と答えたのは22人、「どちらも得意」と答えたのは10人でした。
このとき、「英語または数学のいずれか一方だけが得意」と答えた生徒は何人でしょうか?
【選択肢】
A:27人 B:15人 C:10人 D:5人 E:7人
【正解】
A(27人)
【解説】
「ちょうど一方だけ得意」=(英語だけ)+(数学だけ)=(英語の人数-両方)+(数学の人数-両方)=(25-10)+(22-10)=15+12=27人
解き方のコツ
まず、与えられた条件を整理して視覚化するために「ベン図」を必ず使うようにしましょう。重複している人数や、片方だけに当てはまる人数を円や仕切りで図示することで、情報が頭でぼんやりするのを防げます。
次に、「何人が・何人ではないか」という問いを明確に設定して、全体−(片方・両方)という式を意識します。例えば「どちらかだけ」の人数=「1つ目合計+2つ目合計−両方」の考え方です。
最後に、数字をベン図に書き込むときには「どこに書くか」を決めておき、見やすく、誤植や書き込みミスを減らすように工夫しましょう。ベン図がごちゃごちゃになると、設問を読み違えやすくなります。
【例題】序列・組み合わせ
【問題】
あるプロジェクトに4名の候補(A・B・C・D)がいます。この中から2人を選んで「リーダー」と「サブリーダー」に任命することにしました。ただし、同じ人物が両方の役割を兼務することはありません。
このとき、リーダーとサブリーダーの組み合わせは何通りあるでしょうか?
【選択肢】
ア:6通り イ:8通り ウ:12通り エ:16通り オ:24通り
【正解】
ウ:12通り
【解説】
役割が「リーダー・サブリーダー」で順序ありなので、順列で数えます。
・リーダーの選び方:4通り
・(その人以外から)サブリーダーの選び方:3通り
・よって 4 × 3 = 12通り。
解き方のコツ
まず、問題文に出てくる言葉を丁寧にチェックしましょう。「リーダーとサブリーダーに任命」「順番がある・順番を考えない」「選ぶだけ」などのキーワードが、「順列(並べる)」「組み合わせ(選ぶ)」のどちらを使うかを決める鍵になります。
次に、公式を使う前に状況(人数・役割・順番の有無)を図または簡単な書き出しで整理してください。4人の中から「リーダー・サブリーダー」という役割が異なり順番も意味を持つため「順列」の公式または応用した考え方が有効です。
最後に、時間制限を意識し、公式を思い出して数字を当てはめる練習を繰り返しましょう。パターンに慣れておけば、試験本番で焦ることなく解けるようになります。
【例題】場合の数
【問題】
あるグループに、女性が4人います。この中から3人を選ぶとき、選び方は何通りあるでしょうか?
【選択肢】
A:2通り B:3通り C:4通り D:6通り E:8通り
【正解】
C(4通り)
【解説】
人をA・B・C・Dとすると、選び方は「ABC、ABD、ACD、BCD」の4通りで重複なし。
解き方のコツ
まず、問題文に「選ぶ」「何通り」「並べる」などのキーワードがあるかを必ず確認しましょう。例えば「並べる・順番を考える」とあれば順列、「選ぶ・組み合わせ」とあれば組み合わせを使います。
次に、公式をひとまず覚えておき、数字を「n C r」「n P r」などに当てはめてみること。迷ったら“順番を考えるかどうか”で公式を見分けるのがコツです。
最後に、出題文に慣れていないと時間を消費してしまうので、類題を素早く何題も解くことで「この形式=この解法」という“型”を身につけましょう。
この流れを習慣化すれば、「場合の数」問題でも時間をかけずに正答に近づけるようになります。
【例題】確率
【問題】
赤・青・黄のボールがそれぞれ2個ずつ入った袋から、ボールを1個取り出します。その後、取り出したボールを戻さずにもう1回取り出します。このとき、2回とも青のボールを取り出す確率はいくつでしょうか?
【選択肢】
ア:1/15 イ:1/12 ウ:1/9 エ:1/6 オ:1/3
【正解】
ア:1/15
【解説】
最初に青を引く確率は2/6=1/3。戻さないので、残りは5個で青は1個。
2回目も青を引く確率は 1/5。
したがって
1/3×1/5=1/15
よって1/15。
解き方のコツ
確率問題でまず意識したいのは、「何を・何回」取り出して「どのような条件」で確率を求めるかを丁寧に整理することです。
次に、問題が「戻す・戻さない(復元・非復元)」「順序あり・なし」「複数段階」かを確認し、それに応じた計算式(例:全体分母・分子の変化)を素早く思い出しましょう。
さらに、「分母×分子」「“または”のルール」など、基本ルールを先に思い出してから数字を当てはめると、迷いが減ります。
最後に、演習で「この形式=こう解く」という感覚を養うことで、短時間でも精度を保った解答が可能になります。
【例題】金額計算
【問題】
文房具店で、1会計につき全品20%引きのクーポンを1枚使えます。
ジュース(200円)を2本とクッキー(300円)を2箱買いました。会計時に消費税10%がかかるものとし、税計算は割引後の合計に対して行います。
このとき、支払総額はいくらになりますか。
【選択肢】
A:860円 B:870円 C:880円 D:900円 E:920円
【正解】
C:880円
【解説】
・小計:ジュース200×2=400円、クッキー300×2=600円→合計1,000円
・20%引き(会計全体に適用):1,000×0.8=800円
・消費税10%(割引後に課税):800×1.10=880円
・1円未満切り捨て:端数なし→880円
解き方のコツ
金額計算では、「割引」「消費税」「合計」などの処理順に注意が必要です。特にSPIでは、割引を先に適用してから税計算するパターンが多く、本問でも同様です。
まずは商品ごとの小計を出し、合計から割引額を引き、最後に税率をかける手順を守りましょう。問題文に「税込・税別」「○%オフ」「端数処理」などの条件があれば、見落とさずに処理することが正解のカギです。
【例題】分割払い
【問題】
ある商品を月々5,000円ずつ、12回払いで購入するとします。
購入時に頭金として10,000円を払いました。分割払いの総額は何円でしょうか?(利子・手数料なし)
【選択肢】
ア:70,000 円 イ:60,000 円 ウ:65,000 円 エ:55,000 円 オ:75,000 円
【正解】
ア:70,000 円
【解説】
・月々の支払い:5,000円×12回=60,000円
・頭金:10,000円
・合計(利子・手数料なし):60,000円+10,000円=70,000円
解き方のコツ
分割払いの問題では、「頭金」と「月々の支払い×回数」の合計で総額を求めるのが基本です。支払回数や金額を取り違えないよう、設問の数字を整理してから計算しましょう。
単純な加算式なので、落ち着いて確実に処理することがポイントです。
【例題】仕事算
【問題】
ある仕事をAさんが1人で行うと12日かかり、Bさんが1人で行うと8日かかります。
この2人が一緒に働くと、仕事を終えるのに何日かかるでしょうか?
ただし、2人の作業量は日によって変わらず、同時に作業を始めるものとします。
【選択肢】
A:4日 B:4.8日 C:5日 D:6日 E:6.5日
【正解】
B:4.8日
【解説】
・Aの仕事率:1日に1/12(仕事/日)
・Bの仕事率:1日に1/8(仕事/日)
・2人一緒だと:1/12+1/8=2/24+3/24=5/24(仕事/日)
・したがって必要日数=1÷5/24=24/5=4.8
解き方のコツ
仕事算は「1日あたりの仕事量=1÷日数」で考えるのが基本です。
AさんとBさんの1日分の仕事量を足し、全体(1)をその合計で割れば、2人でかかる日数が出せます。分数の計算に慣れておくと、解くスピードが格段に上がります。
【例題】速度算
【問題】
ある道路を車で移動しています。
目的地までの距離は120 kmです。途中、最初の60 kmを時速60 kmで走った後、残りの60 kmを時速30 kmに落として走行しました。
目的地までの到着にかかった合計時間は何時間でしょうか?
【選択肢】
ア:2時間 イ:2.5時間 ウ:3時間 エ:3.5時間 オ:4時間
【正解】
ウ:3時間
【解説】
・前半60kmを時速60km→時間=60/60=1時間
・後半60kmを時速30km→時間=60/30=2時間
・合計時間=1+2=3時間
解き方のコツ
速度算の鍵は、「距離=速さ×時間」という公式を基に、まず時間を求めることです。
段階ごとに移動距離と速さが変わる場合、「各区間の時間を出して足す」という流れを意識しましょう。総時間を求めやすくなります。
【例題】割合
【問題】
ある映画館でチケット料金を30%値上げしました。すると販売枚数が20%減少したものの、売上高は上昇しました。では、価格値上げと枚数減少があった後の売上高は、何%増加したことになるでしょうか?
【選択肢】
ア:1.0% イ:2.0% ウ:4.0% エ:6.0%
【正解】
ウ:4.0%
【解説】
・売上=価格×枚数
・価格は30%値上げ→1.3倍
・枚数は20%減少→0.8倍
・そのため新しい売上は1.3×0.8=1.04(4%増)
解き方のコツ
割合問題を解くコツは、「基準値を1(または100%)に置き換えて増減を反映させる」ことです。
まず値上げ・値下げ・人数増減などの変化を「×1.30」「×0.80=(1−0.20)」などの数値に置き換えます。続いて、収入や数量など求めたいものにその変化率をかけることで、簡潔に答えを導けます。
文章の中の「何%増えた?」「何%減った?」という問いを見逃さないように注意しましょう。
SPI非言語対策におすすめな問題集・アプリ
SPI非言語分野は、慣れと地道な演習の積み重ねがカギとなります。
問題集で繰り返し対策するほか、スキマ時間を有効に活用できるアプリなども使い対策するとよいでしょう。
おすすめの問題集
SPI非言語分野の対策には、自分で選んだいくつかの問題集を繰り返し学習することが有効です。
下記のような対策系の問題集を使い、分からない領域を一つひとつ潰していくようにしましょう。
これが本当のSPI3テストセンターだ! 2027年度版
価格:1,650円(税込)
著者:SPIノートの会
出版社:講談社
出版日:20250117
商品紹介ページへのリンク:
出版社公式:https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000407372
Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4065383943
【おすすめポイント】
受検者最多の「SPIテストセンター」を想定した一冊。SPI対策でどれを選べばわからないときはとりあえずこれを一冊対策しておけば◎。出題範囲を頻度順に圧縮し、組問題や回答形式別の“時間内に正解する”ための手順を徹底。受検の流れや企業に送付される報告書の理解も促し、本番想定の演習で安定して7〜8割を目指せます。
これが本当のWebテストだ!(1)2027年度版【玉手箱・C-GAB編】
価格:1,650円(税込)
著者:SPIノートの会
出版社:講談社
出版日:20250117
商品紹介ページへのリンク:
出版社公式:https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000407369
Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4065383919
【おすすめポイント】
自宅受検型のWebテストでトップシェアの「玉手箱」と、「テストセンター方式の玉手箱」C-GABにも対応した一冊。言語・計数・英語・性格まで主要形式を“見分け方→解き方→演習→模試”で段階攻略。実施企業が多い検査だけに、形式差の注意点や最新の監視型Webテストにも触れ、初学者でも短期で点を伸ばせる構成です。
2027最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集
価格:1,650円(税込)
著者:オフィス海
出版社:ナツメ社
出版日:20250421
商品紹介ページへのリンク:
出版社公式:https://www.natsume.co.jp/np/isbn/9784816377006/
Amazon:https://amzn.asia/d/4ivvWpZ
【おすすめポイント】
“青本”の定番。2003年の初版から長年に渡り就活生に愛されてきた名著の最新改訂版です。SPIの最新傾向を反映し、言語・非言語に英語/構造的把握力/性格まで広くカバー。復元問題と実戦模試で“スピード×正確性”の両立を狙う構成で、基礎固め後のスコア底上げや本番直前の仕上げに最適です。
おすすめのアプリ
参考書の他に、スマホからアプリで対策することもおすすめです。
通学中や授業の合間など隙間時間で手軽に対策できる点が魅力的でしょう。実際に自身でいくつかのアプリを試してみて、一番しっくりくるものを繰り返し学習するとよいでしょう。
まとめ
SPI非言語の問題は、ただの計算力だけでなく「考える力」も問われるからため、苦手意識を持つ就活生も少なくありません。しかし、出題形式のパターンを知り、頻出の例題に慣れておくことで、着実に得点力は伸びていくのです。
それぞれの問題の解答のコツを掴み、地道に演習を重ねることが合格への近道です。SPIを“苦手な選考における難所”で終わらせず、自信に変えて選考に臨みましょう。
人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!
ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。
・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く
・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ
・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント
・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催
・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる
ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。