今回の記事では、就活の準備段階だからこそ知っておきたいJTの“中の人の声”が満載で、企業理解が一気に深まる「採用担当者によるパネルトーク」をお届けします。
各カテゴリの採用担当が「JTおよびカテゴリを選んだ理由」や「そのカテゴリの魅力」について、自身の経験を基にお伝えし、さらにはカテゴリの垣根を越えた業務や人のつながりについても語っていただきました。
JT採用担当パネルトーク
【登壇者プロフィール】
■飛田 直哉(2010年入社)
初期配属はR&D。R&Dで複数の領域に携わった後、現在はCountry P&C RecruitmentにてR&Dカテゴリ採用担当。
■米倉 佳蓮(2021年入社)
初期配属は原料調達。西日本原料本部にて葉たばこの耕作支援に携わった後、現在はCountry P&C Recruitmentにて原料調達カテゴリ採用担当。
■沼田 真奈(2017年入社)
初期配属は製造。九州工場にてたばこの原料加工に携わる。その後、北関東工場の品質管理を経て、現在はTokyo Officeにてサプライチェーンマネジメントの新卒採用・成長支援を担当。
※サプライチェーンマネジメントカテゴリは、たばこの製造に携わる方を募集する採用カテゴリとなっております。
■松永 隆司郎(2017年入社)
初期配属は営業。静岡支店、東京支社を経て、現在はCountry P&C Recruitmentにて営業カテゴリ採用担当。
■岡戸 祐樹(2023年入社)
経験者採用での入社。前職は金融機関で予実管理や海外事業管理を経験。現在はコーポレート部門の経理部にてファイナンス領域の人事業務を担当。
※ファイナンスカテゴリは、たばこを含む事業部門からJT全体にかかわるコーポレート部門まで、各部門の中にあるファイナンス業務に携わる方を募集する採用カテゴリとなっております。
■羽田 真実子(2021年入社)
初期配属は製造。友部工場にて総務・人事労務に携った後、現在はCountry P&C Recruitmentにてボーダレスカテゴリ採用担当。
※ボーダレスカテゴリは、あらゆる職種(※研究開発職/エンジニア職/アグロノミーテクニシャン職等の一部の専門職種を除く)が初期配属の候補になります。幅広いJTのビジネスの中から中長期のキャリアプランを見据え、初期配属を選定する採用カテゴリとなっております。
【パネルトーク】
司会者:
JT様の各カテゴリから総勢6名の皆さまにご登壇いただきまして、”採用担当パネルトーク”という形で様々なことを伺っていければと思います。
余談ですが、JT様ということで皆さまの中でたばこを吸われる方はいらっしゃいますか?
(飛田、米倉、松永、岡戸が手を挙げる)
なるほど、沼田さまと羽田さまはたばこを吸われないんですね。吸う方も吸われない方も特に関係なくご活躍されてらっしゃるのですね。
それではまず、「なぜJTを選び、カテゴリを選択したのか」ということについて聞いていきましょう。
質問「就活でJTを選び、カテゴリを選択した理由は?」
飛田(R&D):
ものづくりの視点で惹かれたのは、JTの研究領域の広さでした。たばこの研究領域というのはすごく広いです!大学で培った専門分野にとどまらず、周辺領域とも行き来しながら新しい相互作用を生む。そんな研究の設計ができる点に魅力を感じ、R&Dカテゴリを志望しました。
決め手になったのは研究所訪問ですね。複数社の研究所を見学した中でも、JTの社員はとにかくフレンドリーで。学生時代の自分に「今どんな研究しているの?」と話しかけてくれ、とても自然体なやり取りの中で話が弾んだのが印象的でした。理系学生は自分の研究に直結するテーマを選びがちですが、その話の中でJTでは“境界を越えてつなぐ”研究の面白さが実感できたのです。人とテーマの距離が近い環境で、領域横断の挑戦ができる、そのリアルな空気感が入社の後押しになりました。

米倉(原料調達):
もともと私は法律(国際関係法)を学んでいましたが、JTの原料調達の仕事を選んだ理由は、文系出身でも“グローバルに携われる実感”と“社会に良い影響を広げる手触り”が得られるからでした。
ゆくゆくはJTの社会貢献を推進する業務に携わりたいと思いつつ、新卒の初期配属では一次産業の最前線である原料領域を志望しました。現場の想いを自分の目で確かめ、納得してキャリアを積み上げるためでした。
入社の決め手は、大学セミナーで出会った原料調達の社員の“人”でしたね。話が面白く温かみがあり、「こういう先輩たちとなら長く働ける」と感じたのです。実際に入社してみると、農家の方々との近い距離感の中で、たばこ製品に欠かせない「葉たばこ」耕作を支える責任感と人の温かさが共存していることに驚きとやりがいを実感しました。

沼田(サプライチェーンマネジメント):
サプライチェーンマネジメントを選んだ理由は、「つくったモノをお客様に届ける」という実感を軸にキャリアを描きたかったからですね。自動車デザイナーの父の影響で、有形の価値を世に出す仕事に惹かれていました。
学生時代に生物学を学ぶ中で、学部の強みは”食品・化粧品・医薬”だと思っていて、自分の関心も“素材と品質に真正面から向き合える領域”にありました。たばこも人が口にする物なので、そこでJTを認識したのが出会いでした。生物系というバックグラウンドで考えた場合、他のR&Dカテゴリや原料調達カテゴリという選択肢もありましたが、最終的には「つくる→届ける」までを一気通貫で捉えられるサプライチェーンマネジメントに惹かれました。
決め手は、学生時代に出会ったJTのサプライチェーンマネジメント担当社員の話でした。葉たばこが製品になり、確かな品質でお客様の手元に届くまでの流れを、現場の温度感をもって語ってくれたことが印象的だったのです。「自分の手で形にする」工程に深く関われること、そしてたばこづくりの現場とお客様の両方に近い距離で価値を生み出せること、そこにやりがいを感じています。

松永(営業):
営業を選んだ理由は、“好きなものを人にシェアする喜び”を仕事にしたかったからです。学生時代、好きなドラマを友人に勧めて「いいね」と共感が返ってくる瞬間がすごく楽しく、大きな喜びを感じていました。就活で「自分が本当に好きなもの」を見つめ直したとき、日常に密着し、強い愛着が生まれるプロダクトとしてたばこにたどり着き、そのたばこを人々にシェアしていきたいと思い、JTへの関心が高まりました。
入社の決め手は、結論からいうと「JTを世界第1位のたばこカンパニーにしたい」という想いが色んな社員と対話する中で強くなったことが大きいですね。
面談で出会ったJTの営業社員との対話の中で、JTがまだ世界で第3位と聞くと悔しい、自分の好きな商品だから世界1位になって欲しいと自然と気持ちが動いていました。「ならばより多くのお客様にJT商品を選択してもらえるよう自分が営業として伝え、広げていきたい」と熱くなり火がつきました。お客様に近い最前線で、JTの商品の魅力を伝え、より多くのお客様に選んでいただく、その役割を担えるのが営業だと確信し、入社を決めました。

岡戸(ファイナンス):
私はこの中では唯一の経験者採用での入社です。前職は金融機関に勤めていたため、少なからずファイナンスに携わっていたものの、実はJT入社当初は人事志望でした。結果として現在は「ファイナンス領域の人財」を対象に、採用や成長支援を担う立場にあります。自身が会計実務に携わっているわけではないからこその難しさはある一方、ファイナンス領域の社員と対話し課題を可視化し、組織全体を見渡して最適な打ち手を設計する。そのプロセス自体に大きな面白さを感じています。
ファイナンスカテゴリは、入社時点での専門性の保有は歓迎するものの、それよりも「数字への知的好奇心」や前向きさ、そして学び続ける姿勢を重要視しています。ファイナンスカテゴリでは、知的好奇心や前向きさを業務の中で発揮していけば、早期に成長していける環境が整っています。
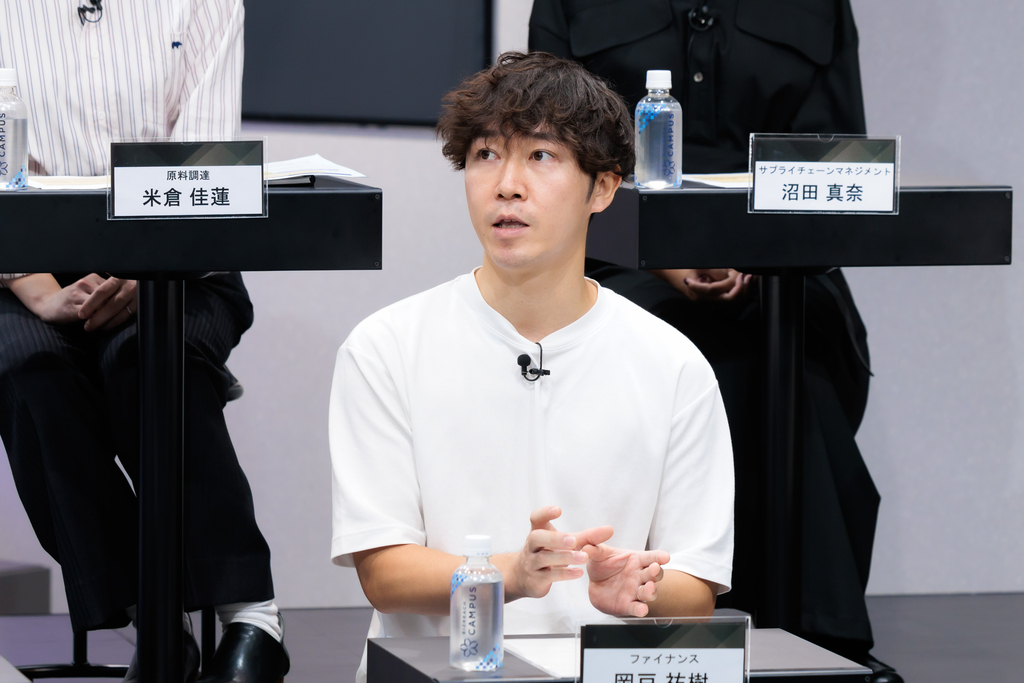
羽田(ボーダレス):
私が入社した頃は「ボーダレスカテゴリ」ではなく、前身のスタッフカテゴリでした。しかも私は選考開始直後にJTを知り、各カテゴリの理解が浅かったため、選考の途中で会社側にカテゴリを決めてもらう「こだわらない」でエントリーしました。そして選考の途中で会社から「スタッフで進みましょう」と案内を受けて、今に至る…という流れです。当時は “自分の適性は会社に見立ててもらおう” と腹をくくっていました。
ただ、もしあの時点でボーダレスがあったら、きっと私はそっちを選んでいたと思いますね。ボーダレスの良さって、「やりたいことはまだ固まっていない、こだわっていないけど、とにかく挑戦したい!」という人にハマる設計です。「この業務がやりたい!この領域で活躍したい!」がはっきりしているなら、それにマッチするカテゴリを選んでいただければと思いますが、「JTの幅広いフィールドの中で自分の力を試したい!チャレンジしたい!」と思った方は、ボーダレスを足掛かりに自身の可能性を広げやすいのではと感じます。

質問「自身が担当しているカテゴリの魅力は?」
司会者:
各部門の魅力についても伺っていきましょう。「皆さまが感じているカテゴリの魅力」について教えてください。
飛田(R&D):
入社後にイメージとのギャップはほとんどなかったですね。むしろ強く感じたのは、社員の「お客様に感動してもらいたい」「愉しんでもらえる商品をつくりたい」という熱量でした。R&Dカテゴリの魅力は、たばこの“おいしさ”を構成する味・香り・吸いごたえなどポジティブな要素を磨き上げる一方で、加熱式たばこを含む“喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品”における安全・安心の検証やリスク評価まで、両輪で取り組める点にあります。メーカーとして責任ある情報と品質で支える、そのバランス感がこの仕事の面白さですね。
また、やりがい的な部分は二層構え、と思っています。お客様の反応という“現場の手応え”に加え、研究成果が特許や他製品への転用技術として結実する瞬間にも、大きな達成感があります。小さなブレークスルーの積み重ねが、最終的に体験価値へつながっていきます。R&Dは、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリングとユーザー体験の間を行き来しながら”価値を形にする”ポジションだと実感しています。
米倉(原料調達):
やりがいは、契約農家の方々と“人対人”で向き合い、役に立てた手応えを現場で実感できることですね。初めて畑に入ったとき、JTの作業着を着ているだけで、若手でも「たばこの先生」と対等に扱っていただける誇らしさと同時に、その期待に応えるための知識・技術を磨かなければという責任感が芽生えました。長年のパートナーとして誇りをもって葉たばこを育てる農家さん、背中で語る先輩社員、“かっこいい大人”に囲まれる環境が原動力になっています。
もう一つのやりがいは、分からないことを曖昧にせず「後日、必ず調べて回答します」と真正面から向き合い、先輩に学び、仮説を検証した上で農家さんに最適解を返せたときです。「あなたに聞いて良かった」と言われる瞬間が、努力の証になります。取り繕うのではなく、誠実さで信頼を積み上げるその姿勢が“本当にかっこいい社員”をつくると実感しています。こういったことを実感できる喜びが、このカテゴリを選んで良かったと思える理由ですね。
沼田(サプライチェーンマネジメント):
サプライチェーンマネジメントの醍醐味は、徹底したチームワークにあります。
たばこは小さな箱に収まる製品ですが、生産管理、設備設計・管理、製品製造、品質管理、原価管理まで、ひとつの工程も“ひとり”では完結しません。毎日、何十件もの連絡や10人超の関係者との調整を重ね、課題を解決しながら、より良いたばこを形にしていきます。工場の仕事=マニュアル通り、というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが全く逆で、むしろ、研究開発や原料調達からのバトンを受け継ぎ、サプライチェーンマネジメントの中でも人と人がつながり合い、より良い製品に「作りあげる」ことで価値に変えていく、その実感がこの仕事の面白さです。
中でも印象に残っているのは、新製品の立ち上げです。入社直後、加熱式たばこ(Ploom S)を自工場で導入するプロジェクトが走りました。紙巻たばこと勝手がまったく違うため、既存設備の設定から品質ルールまでゼロから再設計する必要があり、現場で何度も会議と試作を重ねました。初号のラインが無事に動き、製品が“最初の一箱”として出てきた瞬間、皆で手を取り合って喜び、達成感を分かち合うその瞬間に、「みんなの想いをつなげて、お客様に自信をもって届けられる製品を形にできた」と胸を張れました。
松永(営業):
営業の醍醐味は、やっぱり“目の前のお客様”がファンになってくれる瞬間です。私たちは出来上がった商品をお客様に届けて、そこで初めて手応えが返ってくる。金銭的な負担やにおいの悩み…暮らしや属性でお客様のニーズは本当にバラバラです。だから販売店様とも連携しつつ、「このエリアでは何をどう提案すれば喜んでもらえるか」を積み上げていく。お客様や販売店様からのご支持って、結局はその積み重ねの先にしかないと思います。まずは目の前の一人のお客様に誠実に向き合う、そこが営業の勝負どころ。
忘れられないエピソードは、お客様から駅前の喫煙所で声をかけられたときです。「君、覚えてる? 半年前に加熱式たばこを勧めてくれたよね。」と言ってもらえたのです!その方はにおいが気になるということで奥様に喫煙を止められていたのですが、加熱式たばこに変えたら奥様から「これなら全然気にならない」とOKが出たそうです。「あれからたばこを続けられているよ!ありがとう!」って笑ってくれました。もし私があの場で加熱式たばこの選択肢を示していなかったら、切り替えという発想は生まれなかったかもしれない。現場で“お客様に提供できる選択肢”を持って、お客様のニーズに一番合う商品を一緒に見つける、それが営業の価値だと、改めて実感しました。
岡戸(ファイナンス):
ファイナンスの魅力は一つ例に挙げると、数字を分析して“その裏側で何が起きているか”を捉えられることだと思います。例えばたばこ製造で言えば、原料・材料の手配や輸送には必ず資金が伴い、その調達や原価管理を含め、背後で全体を支えるのがファイナンスです。事業の流れを数字で可視化しながら、次の一手を設計していきます。見えにくいところで価値を生む、そこにやりがいを感じる社員は多いと言います。
もう一つの面白さは、数字という“共通言語”を武器に、若手でも上位者に対して経営に関わる分析・検討・提案ができる点です。具体的には、数字という事実に基づき、戦略立案や資源配分など、経営に近い論点に踏み込めるのは、このカテゴリならではです。案件の規模はさまざまでも、意思決定の質を高め、会社経営・事業全体を支える実感が持てることが、JTのファイナンスで働く醍醐味だといえます。
羽田(ボーダレス):
ボーダレスカテゴリの魅力は、バリューチェーン全体と関わりながら“人と人をつなぎ、組織を動かす”力が磨けることですね。配属先が変われば相手も仕事の文脈もがらりと変わりますが根っこは同じで、お互いにリスペクトを持って情報や目的を共有し、同じゴールに向かってみんなで協働すること。ここはどこに行っても変わらず、大切なことです。
それを体感したのが入社2年目のとき。自分起因のミスを“迷惑かけたくない”一心で黙って自分で何とか対応しようとしてしまっていたとき、上長に呼ばれてめちゃくちゃ叱られたのです。JTには前向きな意味で“失敗に寛容”という文化がありまして、ただしそれは、誰かのミスを皆でカバーする前提として、全員がお互いに誠実であることが条件だと。そのためには抱え込まずに正直に打ち明けることが第一歩だと叱られました。失敗も含め一人で抱え込まないでチームに共有することで、より強い組織がつくれると学びました。部門が変わっても、この経験から学んだ作法だけは守り続けています。

質問「カテゴリごとのつながりは?」
司会者:
それぞれの魅力について伺ったところで、カテゴリを横断した連携についても聞いていきましょう。
飛田(R&D):
カテゴリ横断のつながりは非常に多いですね。
R&Dはいわゆる“上流工程”ですが、出発点は一つではありません。研究所や開発センターが持つ知見・技術資産を磨いて新しい提案をするケースもあれば、営業からの顧客インサイト、サプライチェーンマネジメントや原料調達の現場知見が起点になることもあります。重要なのは、最終的に満足していただくのはお客様だという視点です。だからこそR&Dだけではなく、他のカテゴリからのフィードバックも早期に取り込み、「次にどんな価値をつくるか」を研究段階から多方面とすり合わせていくことが大切です。
そして良い技術が生まれても、コストや価格の整合が取れなければ良い製品にならない。ファイナンスと収益性を詰め、サプライチェーンマネジメントと量産性を検証し、マーケティングや営業と市場適合性を磨き込む。この連携の密度こそが、研究を“使える価値”へと変えていくのです。
米倉(原料調達):
特にR&Dの「葉たばこ研究」との連携は密で、産地の悩みを研究テーマへと橋渡ししたりしています。例えば「この地域は葉たばこの病気の広がりが早く、収量が確保できない」「管理作業の負担が大きい」といった現場の声を研究側へ共有。すると「病害に強い新品種の開発」「栽培管理がラクになる新品種の開発」といった解決策が立ち上がるのです。
開発された品種は、原料側が“逆輸入”する形で産地へ普及します。結果として農家の収量・収入の安定や、原料の品質向上といった成果が出る。そんな好循環を現場と研究の連携で実現していきます。現場の課題を科学に変えて、科学の成果を再び現場に戻す。原料調達は、その循環の中心でJTのものづくりを底上げしています。
沼田(サプライチェーンマネジメント):
サプライチェーンマネジメントも、日々いろんなカテゴリと行き来して仕事していますね。
最も密なのはR&Dと営業です。R&Dとは、新製品をつくるときや既存品をアップデートするときに、工場まで来てもらって一緒にラインを見ながら「ここは改善が必要」「ここは狙い通り動いている」と細かく擦り合わせます。営業とは需給面での連携が中心。どれだけお客様に必要とされているかを踏まえて、「じゃあどれだけ、いつまでに作る?」を具体の数に落としていきます。原料調達とも、製品にする前の葉たばこの処理などの調整があります。
加えて、サプライチェーンマネジメント出身の社員がR&D・原料調達・営業の需給担当などへ異動するケースも多く、人の行き来という意味でも結びつきは強いです。さらにファイナンスやスタッフとも、原価管理や総務、生産管理の実務で顔を合わせることが多い。要するに、工場を動かし製品を届ける上で、ほぼ全てのカテゴリと肩を並べて進むのがこの仕事です。
松永(営業):
営業の中には、サプライチェーンマネジメントと需給調整を担うLogistics & Adimin.という部署があります。現場の販売実績などを踏まえて、「いつ・どれだけの供給が必要か」を設計し、サプライチェーンマネジメントと調整していく流れです。
同時に、マーケティングを介してR&Dとも密接に結び付きます。お客様の声や、販売実績など、営業が日々ためている一次情報を本社営業が集約した後、マーケティングで整理して改善点や新商品の方向性を具体化し、R&Dへバトンを渡し次なる商品改善に接続します。現場の気づきを社内に還流させ、需給計画から商品改良までをつないでいく、それが営業の大きな役割の1つだと思っています。
岡戸(ファイナンス):
ファイナンスは全カテゴリと日常的に交差します。分かりやすいところではサプライチェーンマネジメントの原価管理。計画よりコストが膨らめば、製造現場の各部署と協力しその最適化を図ります。営業面では、期初計画に対する実績の進捗を追い、上振れ・下振れの要因を分析し、必要に応じて資源配分の調整を提案します。各種数字を通じて動向を把握し、必要なアクションの検討および関係部署への提言をしています。
また、ファイナンスの中でも制度会計・税務・財務等は、特定のカテゴリというよりも会社運営を支える役割を担っています。会社の中で「お金」と切り離せる仕事はなく、ファイナンスは日々、全社の意思決定に寄与しています。R&D・原料・サプライチェーンマネジメント・営業・スタッフまで横断し、数字という共通言語で現場や外部ステークホルダーと経営をつなぐわけです。数字を扱い高度な専門性をもって企業価値の最大化の一翼を担えることが、ファイナンスの大きなやりがいだと感じています。
羽田(羽田):
ボーダレスは、実務としてはほぼ全ての部門と関わりますね。そしてゆくゆくはスタッフ職に進む方が多いのですが、大きく2パターンがあります。
まず一方は、マーケティングやカスタマーサティスファクションのように、お客様や販売現場と直接向き合いながら、他カテゴリと連携して価値提供を磨く領域。もう一方は、例えば私たちのように人事で採用に携わるような、バリューチェーンの最前線に直接は立たないものの、組織づくりを通じて事業を下支えする領域です。どちらの道でも最終的に見据えるのは“お客様”。お客様に価値を提供することにつなげるという意味で、目指すゴールは同じだと捉えています。
この2パターンのキャリアの選び方に決まった正解はありません。時期や経験、興味関心によって幅広く経験する人もいれば、どちらかに腰を据える人もいます。大切なのは、その時々で「自分はどのような形・方法でお客様に価値を提供していきたいか」を自分の言葉で考え続けていくことです。
司会者:
普段何気なく接しているたばこという嗜好品が、多くの社員の想いに支えられて私たちの手元に届いている、ということを感じられるパネルトークでした。
学生の皆様は、ぜひJT様の動画やHP、イベントを通じて、その魅力を深掘りしていただければと思います。
皆さま、今日はありがとうございました!

こちらの採用担当パネルトークに加え、会社説明や各カテゴリの紹介を含めた動画はこちらです。
パネルトークで展開された社員同士の会話の雰囲気も見どころです。ぜひこちらもご覧ください。
https://youtu.be/kRpjdfNzsiU
